creative
ホームページ制作
2025/07/15
【成約率向上】WEBサイト提案書テンプレート|作成時のポイントも解説します!
#creative
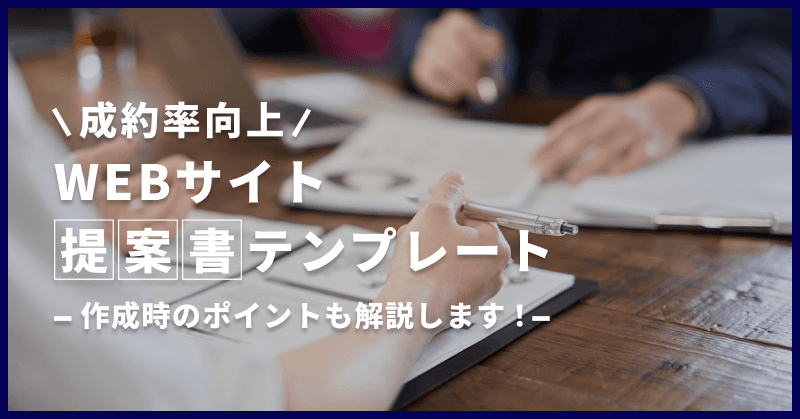
こんなことに悩んでいませんか? ・Webサイトのリニューアルを提案したいが、どんな資料を作ればいいか分からない ・制作会社に丸投げするのは不安…でも自社でゼロから作る時間もスキルもない ・稟議書が通らず、リニューアルのチャンスを逃してしまいそう 実は、その悩み、無料で使える提案書テンプレートですぐに解決できます。 この記事では、社内承認が通るWebサイト提案書テンプレートと、失敗しないための作成ポイントを解説します! この記事でわかること ・稟議が通る提案書に「必ず入れるべき10の項目」とその理由 ・経営層に伝わる「構成」「KPI」「費用感」の整理方法 ・Webの専門知識がなくても使える無料テンプレートの活用法
目次
1.【無料ダウンロード】WEBサイト制作の提案書テンプレート
2.WEBサイト制作の提案書に必要な項目
2-1.背景
2-2.目的
2-3.現状の課題
2-4.ターゲット
2-5.KPI
2-6.サイト構成
2-7.デザインコンセプト
2-8.機能要件
2-9.スケジュール
2-10.費用感イメージ
3.WEBサイト制作の提案書の作成ポイント
3-1.端的に内容をまとめる
3-2.専門的な用語はなるべく使わない
3-3.視覚的な要素を多くする
3-4.統一感のある資料にする
4.WEBサイトの提案書でよくある5つの失敗
4-1.目的が不明瞭
4-2.デザインが先行している
4-3.運用フローの説明が欠如
4-4.見積もりが不透明
4-5.リスクの説明不足
5.まとめ|WEBサイトの提案書テンプレートをダウンロード
【無料ダウンロード】WEBサイト制作の提案書テンプレート
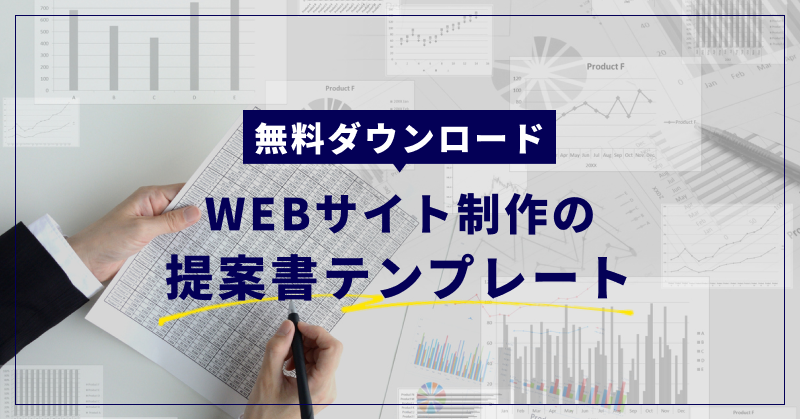
「社内向けにWebサイト制作やリニューアルを提案したいが、ゼロから提案書を作る時間もノウハウもない...」
そんな方のために、すぐ使える提案書テンプレートを無料配布しています。
上司や役員への稟議・プレゼン時に必要な要素をコンパクトにまとめられる構成になっており、「背景・目的・構成案・費用・KPI」などの基本項目を網羅。
Web制作の知識がなくても、必要な内容を漏れなく記載できる設計です。
以下よりテンプレートをダウンロードできますので、自社用に自由に編集してご活用ください。
WEBサイト制作の提案書に必要な項目

提案書の成否は「どこまで的確に要素を押さえているか」で決まります。
Web制作の専門知識がなくても、発注先や社内の意思決定者に伝わる提案を行うためには、構成の基本を理解しておくことが重要です。
この章では、提案書に必ず盛り込むべき10の項目を解説します。
- ・背景
- ・目的
- ・現状の課題
- ・ターゲット
- ・KPI
- ・サイト構成
- ・デザインコンセプト
- ・機能要件
- ・スケジュール
- ・費用感イメージ
背景
プロジェクトの出発点となる「背景」は、なぜWebサイトを制作・リニューアルするのかを端的に説明するパートです。
市場環境の変化、競合サイトの進化、採用強化など、経営層に伝わる言葉で説明しましょう。
具体的なトリガーがある場合(例:展示会出展、新製品ローンチ)も明記すると、説得力が増します。
目的
提案書において「目的」は全体の方向性を決める最重要要素です。
Webサイトを通じて何を達成したいのかを、売上・採用・広報の3カテゴリに分類し、明確な数値目標として一文で言い切りましょう。
例:「年間商談獲得数を1.5倍に」「月間応募数を20件確保」「企業認知を前年比1.2倍へ」。
目的が曖昧だとページ構成や訴求軸もぶれやすくなり、稟議を通す説得力も弱まります。
社内で合意されたゴールを明文化し、冒頭に掲げてください。
現状の課題
Webサイトのリニューアル提案では、現状の課題を「流入」「導線」「更新体制」の3つの視点で整理することが重要です。
たとえば「検索経由の訪問が少ない」「ページビューはあるがCVにつながっていない」「社内で情報更新ができず古いまま放置されている」といった具体的な課題を、GA4のデータやヒートマップを用いて可視化しましょう。
スクリーンショットを1枚添付するだけでも説得力が増します。
原因分析を曖昧にせず、具体的な数値や行動データをもとにした改善提案へつなげてください。
提案書の説得力を高めるには、事実ベースで「どこにどんな課題があるか」を可視化することが不可欠です。
ターゲット
誰に向けたWebサイトなのかを明確にすることで、コンテンツの構成やデザインの方向性が定まります。
営業支援を目的とする場合は「業種・役職・課題・意思決定プロセス」まで整理されたペルソナを定義し、CV導線設計に活用します。
要素 | 内容例 |
業種 | 製造業(OEM/精密加工) |
役職 | 課長〜部長クラス |
主な課題 | 新規発注先の開拓・技術力の見極め |
意思決定者 | 社長または役員会 |
情報収集手段 | 検索/展示会後のWeb調査 |
KPI
KPI(重要指標)の定義は、サイトの目的に対する進捗を可視化するうえで不可欠です。
BtoBサイトであれば「CVR(問い合わせ率)」「商談化率」「平均受注単価」「平均受注までの期間」などを軸に、サイト施策が最終的な売上にどうつながるかを明確に示しましょう。
ROI(投資対効果)の概算式をあらかじめ提案書に盛り込むと、上層部の意思決定を後押しできます。
指標項目 | サンプル値 | 備考 |
CVR | 1.2%(現状)→2.5% | 平均より低く改善余地あり |
商談化率 | 40% | 問い合わせ後の商談率 |
平均受注単価 | 180万円 | 顧客1社あたりの契約金額 |
受注までの期間 | 約2.5ヶ月 | リードタイム短縮が次の課題 |
投資回収期間目安 | 約6ヶ月 | 制作費回収までの期間 |
サイト構成
提案書には、現状サイトと提案サイトの構成を比較しながら、ユーザー導線をわかりやすく可視化することが求められます。
とくに製品数やサービスが複数ある場合は、トップページから詳細情報、資料請求・お問い合わせまでの流れを階層的に整理しましょう。
構成をマップ図や表に落とし込むことで、サイト全体像が直感的に伝わります。
ページの追加・統廃合なども明示すれば、社内での合意形成を促進できるでしょう。
階層 | 旧構成 | 提案構成(新) |
トップ | トップ | トップ+ヒーローバナー |
第1階層 | 会社概要/製品情報 | 導入事例/製品カテゴリ別構成 |
第2階層 | お問い合わせ | 資料DL/お問い合わせCTA導線追加 |
その他 | 社内報/ブログ(活用少) | 活用停止→採用情報に一本化 |
デザインコンセプト
デザインは見た目だけでなく、情報伝達の「戦略」です。
ターゲット層の好みに合わせて、トンマナ(色・フォント・写真のテイスト)を定義し、参考サイトや競合ベンチマークも添えると、社内メンバーの認識を揃えやすくなります。
特にBtoB企業では「信頼性」「技術力」「スピード感」を視覚的に表現することが重要。
ブランドカラーや写真の方向性は、公開後の更新作業にも影響するため、初期段階での合意形成が欠かせません。
機能要件
Webサイトの機能要件は、見積もり・制作期間・保守体制に大きく関わるため、あらかじめ「必要なもの」「あると便利なもの」に分類して整理しましょう。
CMS(WordPressなど)やMAツールとの連携、SSL対応、多言語展開、アクセシビリティ(JIS X 8341-3:2016)の準拠など、業種・目的によって必要な機能は異なります。
要望を曖昧にしたまま進めると、後工程で追加費用やスケジュール延長につながるため、初期段階で一覧化しておくことが肝要です。
区分 | 要件 | 必須/任意 | 備考 |
CMS導入 | WordPress 等の導入 | 必須 | 社内更新を想定する場合 |
MA連携 | HubSpot/Salesforce等 | 任意 | リード育成が必要な場合 |
お問い合わせ | フォーム+自動返信メール | 必須 | スパム対策も検討 |
多言語対応 | 英語/中国語など | 任意 | 海外取引がある場合 |
SSL対応 | HTTPS化(常時SSL) | 必須 | セキュリティ対策 |
アクセシビリティ | 色のコントラスト/代替テキスト | 任意 | 官公庁・福祉系で特に重要 |
スケジュール
提案書には、全体の制作スケジュールをガントチャート形式で明示することが効果的です。
中小企業向けのWeb制作では、要件定義から公開までおおよそ4〜6ヶ月が目安とされています。
ただし、ページ数や機能によっては短縮・延長の余地があるため、各工程の工数感を明確にし、社内体制(チェック者や稟議ルート)も踏まえた現実的な計画を示すことが重要です。
スケジュールの曖昧さは、信頼を損なう原因になります。
費用感イメージ
Webサイト制作の費用感は、ページ数・機能・CMSの有無によって大きく異なります。
LISKULの調査によれば、もっとも簡易な構成でも20万円程度から、CMSや機能追加があると+30〜80万円程度が相場です。
詳しくはこちらの記事をご確認ください。
ホームページリニューアルの費用相場は?安く抑える方法や失敗しないコツも解説します!
WEBサイト制作の提案書の作成ポイント

提案書の成否は「読みやすさ」で決まります。
特にWeb制作のような専門的テーマでは、相手が非デジタル人材であるケースも多いため、資料の伝わりやすさが重要です。
この章では、提案内容を的確に伝え、社内承認をスムーズに通すための作成ポイントを4つに絞って解説します。
読み手の視点を常に意識し、「理解される提案書」を目指しましょう。
端的に内容をまとめる
提案書では、冗長な説明よりも「要点だけ」を簡潔に提示する方が圧倒的に伝わります。
特に経営層向け資料では、「結果どうなるのか」を1ページ内で端的に伝えることが求められます。
「現状→課題→解決策→期待効果」の流れを1枚で表現する“1スライド1メッセージ”の原則を守ると、プレゼン効果も高まります。
全体構成を組む段階から、各スライドの主張を一言でまとめてみましょう。
専門的な用語はなるべく使わない
CVRやUX、CMSなど、業界では当たり前の略語や専門語も、相手が非デジタル人材であれば通じない可能性があります。
提案資料では、できるだけ「誰にでも伝わる表現」に言い換えることが大切です。
どうしても専門用語を使う場合は、以下のように簡単な解説を添えましょう。
専門用語 | わかりやすい表現例 | 解説補足 |
CVR | 問い合わせに至った割合 | 100人中何人が行動したかを示す指標 |
CMS | 社内で更新できる仕組み | WordPressなどの管理画面のこと |
SEO | Googleで上位に出す施策 | 検索エンジンでの表示順位を上げる方法 |
“わかりやすさ”は読み手への配慮です。
専門性よりも伝達性を優先しましょう。
視覚的な要素を多くする
提案書は「読ませる」ものではなく「見て伝わる」ものにすべきです。
長文よりも、図・表・グラフ・イメージ画像を積極的に使うことで、理解力と説得力が格段に向上します。
特にWebデザインの企画書では、構成案やデザインイメージを視覚で示すことで、完成形の具体性が伝わりやすくなります。
- ・サイトマップ図(トップページ→製品→資料DL→問合せなど)
- ・KPI推移の棒グラフ(CVRやUU数の見通し)
- ・トンマナ比較のビジュアル(競合3社のキービジュアルなど)
こうしたビジュアル資料を各セクションに1つ以上入れるだけで、資料の印象は大きく変わります。
読み手が「頭で理解する前に目で納得できる」資料を目指しましょう。
統一感のある資料にする
どれだけ内容が優れていても、体裁に統一感がなければ説得力は半減します。
文字サイズ・フォント・色・余白・図表の使い方など、見た目の整合性を保つことで、「ちゃんとした会社が作った」印象を与えられます。
特にPowerPointやGoogleスライドで作成する場合、以下のルールを資料全体に一貫させましょう。
項目 | 推奨設定例 |
フォント | メイリオ、Noto Sansなど視認性高いもの |
文字サイズ | 見出し24pt/本文18pt以上 |
色使い | 2~3色に絞る(ベース・アクセント) |
図表のスタイル | 罫線や色合いを統一 |
余白 | 上下左右に十分なスペースを確保 |
読み手は「文章」ではなく「印象」で判断します。
内容と同じくらい、視覚面の完成度にも配慮しましょう。
WEBサイトの提案書でよくある5つの失敗

どれだけ良い構成やデザインでも、「説得できない提案書」では意味がありません。
実際、多くのWebサイト制作の企画書・プレゼン資料は、基本的なミスで社内承認が通らずやり直しになるケースが散見されます。
このパートでは、特に中小企業がやりがちな5つの失敗とその回避策を紹介します。
共通するのは「構想が浅い」「読み手視点が欠けている」ことです。
目的が不明瞭
「サイトをきれいにしたい」だけでは決裁は通りません。
提案書には、KGI・KPIに基づいた具体的な目的を明示する必要があります。
たとえば「問い合わせ件数を月20件以上に」「新卒採用で年間30名の応募獲得」など、定量的な成果目標があるか否かで説得力が大きく変わります。
目標があいまいなままでは、構成もデザインもブレる要因になります。
明確な目的は全体の軸となり、稟議通過率を高めます。
デザインが先行している
ビジュアルから入ると、情報設計が破綻します。
よくあるのが「先にトップページデザインを制作し、後からページ構成をはめ込もうとする」パターンです。
これでは、訴求順序や導線に矛盾が生じ、ユーザーが迷いやすいサイトになります。
サイトリニューアルでは、まずコンテンツ構成と導線設計を固めてからデザインを落とし込むのが鉄則です。
運用フローの説明が欠如
制作時は順調でも、公開後に「誰も更新しないサイト」になるケースは少なくありません。
これは、運用フローや社内体制を提案書で示していないためです。
以下の項目が記載されていないと、将来的な放置・属人化・情報陳腐化につながります。
- 更新担当者と工数(社内か外注か)
- 更新頻度と運用ルール
- CMS導入の有無
制作後の運用まで見据えた提案でこそ、経営層の信頼が得られます。
WEBサイトの運用保守はBPOサービスで対応することもおすすめです。
見積もりが不透明
見積書に「一式」や「詳細未定」が多いと、不安感が増し稟議が通りません。
特に多いのが、ページ単価・機能追加・CMS構築費などの曖昧な表現です。
これにより、公開直前で「追加請求」が発生し、社内トラブルになるケースもあります。
以下のように、見積もり内訳を表形式で示しましょう。
項目 | 内容 | 単価 | 数量 | 小計 |
トップページ | デザイン+コーディング | ¥60,000 | 1 | ¥60,000 |
下層ページ | 汎用テンプレート対応 | ¥30,000 | 5 | ¥150,000 |
CMS構築 | WordPress導入+初期設定 | ¥80,000 | 1 | ¥80,000 |
透明性がある見積りが、合意形成と信頼獲得の近道です。
リスクの説明不足
Web制作には必ず“想定外のコスト”や“トラブルリスク”が伴います。
よくあるのが、リニューアル後に検索順位が下落したり、メール・SSL設定で不具合が起きるケース。
しかし多くの提案書では、こうしたリスクへの対策や事前説明が欠けており、万一の際に信頼を失う原因になります。
- SEO順位変動のリスク
- サーバー・ドメイン切替時の障害リスク
- CMS移行による表示崩れ
これらを「想定リスク」として明示し、対応方針を提示しましょう。
まとめ|WEBサイトの提案書テンプレートをダウンロード

Webサイト制作における提案書は、単なる「説明資料」ではなく、社内を動かすための“意思決定ドキュメント”です。
今回紹介した要素を押さえることで、説得力と実行力を兼ね備えた提案が可能になります。
特に重要なのは以下の5点です。
- 目的・KPIの明確化:数字で語れる目標があるだけで、稟議通過率が段違いに上がる
- 構成・デザインの整合性:情報設計 → ビジュアルの順に構築するのが基本
- ターゲット定義と改善根拠の可視化:GA4やヒートマップ等、データに基づいた訴求が不可欠
- 運用・費用・スケジュールの透明化:曖昧さがあると、承認も信用も得られない
- 資料の視覚性と統一感:内容だけでなく、見た目も「ちゃんとしてる」かが問われる
これらの要点を反映したテンプレートを使えば、誰でも短時間で完成度の高い提案書が作成できます。
貴社のWeb施策が「伝わる提案書」から始まることを願っています。
このまとめを読み返すことで、「なぜ自社の提案が通らなかったのか」が少し見えてきた方も多いのではないでしょうか。
この記事を書いた人
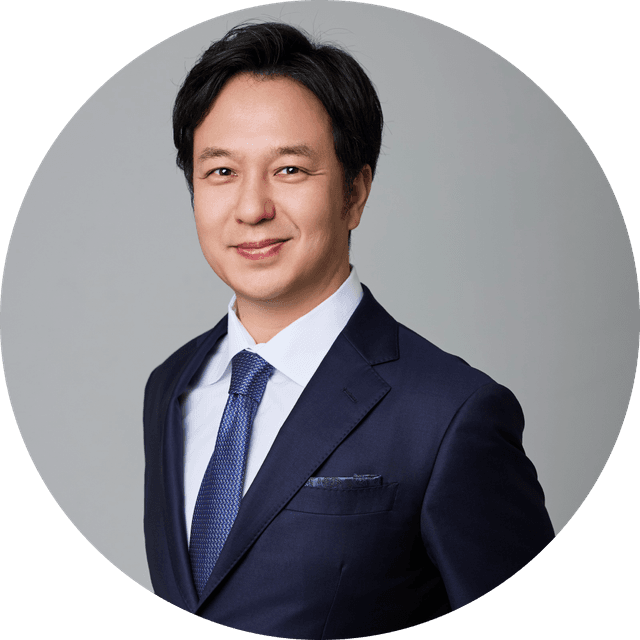
株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人
不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。

