in-house
マーケティング
2025/04/20
近年はWEBマーケティングが内製化しやすい?注目される背景や失敗を防ぐポイント
#in-house

目次
1.WEBマーケティングの内製化を図るメリット
1-1.外注費の削減
1-2.長期的な維持費からの脱却
1-3.お客様のニーズを即座に反映できる
1-4.ナレッジを自社に蓄積でき活用できる
1-5.コミュニケーションコストの削減
2.近年、WEBマーケティングの内製化が注目される理由や背景
2-1.AI技術の進歩や自動化ツールの発展
2-2.フリーランスや外部専門家の活用がしやすくなった
2-3.無料・低価格の学習機会の増加
3.内製化の失敗を防ぐための重要なポイント
3-1.最初から全て内製化しない
3-2.人材やリソースの確保は余裕を持って準備する
3-3.部分的に専門人材を登用する
3-4.ナレッジ共有・蓄積の仕組みを念入りに整える
4.効率的に行うなら内製化支援サービスを利用するべき
4-1.プロが最適な体制を提案してくれるから
4-2.採用支援も受けられるから
4-3.時間とリソースを節約できるから
4-4.ソフトの選定や環境構築を担ってくれるから
5.WEBマーケティングの内製化支援会社
5-1.株式会社デイワン
6.まとめ|WEBマーケティングの内製化について
WEBマーケティングの外注費が膨らみ続ける一方で、肝心の成果はイマイチ。
施策の中身にはほとんど関われず、どこか他人事のように感じていませんか?
外部任せのマーケティング運用に限界を感じ始めた今こそ、「内製化」が現実的な選択肢となりつつあります。
近年は、AIツールや自動化ソリューションの進化により、専門知識がなくても社内で広告運用を行うことが可能に。
初期設定さえ整えれば、あとはAIが最適化を担い、費用対効果の高い施策を継続的に実現できます。
この記事では、
- 内製化を図るメリット
- 内製化が注目される背景
- 失敗を防ぐためのポイント
を解説します。
外注費を抑え、変化に即応できる柔軟な体制を目指したい方は、ぜひ読み進めてください。
また、内製化の進め方や重要なポイントを実際の成功事例を元に解説したお役立ち資料もぜひダウンロードください。
WEBマーケティングの内製化を図るメリット

WEBマーケティングを内製化することは、単なるコスト削減にとどまらず、社内にノウハウを蓄積し、柔軟でスピーディな運用体制を築くことに直結します。
以下では、内製化によって得られる5つの主なメリットを解説します。
- 外注費の削減
- 長期的な維持費からの脱却
- お客様のニーズを即座に反映できる
- ナレッジを自社に蓄積でき活用できる
- コミュニケーションコストの削減
外注費の削減
WEB広告やコンテンツ制作を外注すると、以下のような費用が発生します。
- リスティング広告・SNS広告の運用手数料(20〜30%)
- コンテンツ制作や改善にかかるディレクション費
- 定例ミーティングやレポート作成の時間コスト
これらを自社で運用することで、年間数十万〜数百万円単位のコストを削減可能です。
削減した費用は、以下のような再投資に活用できるでしょう。
- 自社マーケターの人材育成
- ツール導入やテストマーケティング
- 成果が高かった広告の再投資
長期的な維持費からの脱却
外注体制では、運用を続ける限り費用が発生し続けるため、長期的な維持費が重くのしかかります。
対して内製化すれば、初期の教育コストこそ必要ですが、継続的にかかる費用は人件費が中心となり、変動費を抑えることが可能です。
中長期的な視点で見れば、運用費の削減とともに自社でのスキル獲得という二重のメリットが得られます。
お客様のニーズを即座に反映できる
お客様のニーズは刻々と変化するため、内製化することで迅速な対応が可能になります。
例えば
- 直近の商談で話題になったトピックをキャッチコピーに反映
- アクセス解析の結果を基にその日のうちにLP修正
- 商品レビューを受けて即座に広告文を調整
こうしたスピード感のある施策実行は、外注では実現しにくい部分です。
社内に運用体制を持つことで、よりタイムリーにユーザーの声を反映したマーケティングが行えるようになります。
ナレッジを自社に蓄積でき活用できる
外注に頼っている多くの会社が、自社のHPやSNSであるのにデータファイルがない、運用方法がわからないなどが多くあります。
結果として、自社コンテンツであるのに情報が貯まらず、分析もできていません。
これらを解消することで、会社の財産であるデータを活用しやすくなります。
蓄積した知見は、新たな施策の立案や人材育成にも有効活用でき、企業のマーケティング戦略の質を継続的に高めてくれます。
コミュニケーションコストの削減
外注先とやりとりしている中で、自社の担当者が退職したり異動したりするタイミングでは、改めて顔合わせや情報共有、引き継ぎが必要となり、その都度多くの手間と時間がかかります。
加えて、外注先とのやり取りでは以下のようなコミュニケーション工数が発生しているはず。
- 案件ごとの説明や背景の共有
- 資料作成や進捗管理表の整備
- 打ち合わせ日程の調整や会議参加
こうした積み重ねが、日常的に大きな負担となっているケースも少なくありません。
内製化によって社内で運用が完結するようになれば、これらの無駄な調整や連携のための時間が大幅に削減できるでしょう。
近年、WEBマーケティングの内製化が注目される理由や背景

WEBマーケティングの内製化は、以前に比べて現実的な選択肢となりつつあります。
技術の進化や働き方の多様化、学習機会の拡大が進んだことにより、専門会社に依存せずとも自社運用が可能になってきたからです。
以下で詳しく解説します。
AI技術の進歩や自動化ツールの発展
AIの活用により、これまで専門家の判断に頼っていた部分がツールで補えるようになっています。
例えば
- リスティング広告の自動最適化(Google広告スマートキャンペーンなど)
- SNSの自動投稿や配信タイミングの最適化
- アクセス解析ツールによるインサイトの自動抽出
こうしたツールを導入することで、少人数でも効果的な運用が可能になり、専門的なスキルを持たない企業でもマーケティング業務の内製化を進めやすくなっています。
フリーランスや外部専門家の活用がしやすくなった
副業解禁やオンライン業務の普及により、優秀なマーケターやデザイナーとスポットで連携できる時代になりました。
そのため、
- 大手企業出身者のノウハウを部分的に導入できる
- 内製チームの穴を外部で一時的に補完できる
- 社員採用よりも柔軟に予算・期間を調整できる
といった柔軟な運用体制が可能になります。
完全な内製にこだわらず、外部リソースを「部分的なパートナー」として使えることが、現代の内製化の強みと言えます。
無料・低価格の学習機会の増加
近年は、WEBマーケティングに関する教育コンテンツが豊富に公開されており、未経験者でも基本的な知識やスキルを習得しやすい環境が整っています。
YouTubeやUdemyをはじめとしたオンライン学習プラットフォームでは、SEO、リスティング広告、SNS運用など多岐にわたる実践的な講座が提供されています。
また、GoogleやMetaといったプラットフォーマーが提供する公式教材も質が高く、無料でアクセス可能です。
これにより、新たに専門人材を雇用せずとも、社内の既存メンバーを育成してWEB施策に取り組めるようになり、内製化へのハードルは大きく下がっています。
内製化の失敗を防ぐための重要なポイント

WEBマーケティングの内製化は多くのメリットをもたらしますが、計画的に進めないと効果が出ないばかりか、逆に混乱を招くこともあります。
以下のポイントを押させることが大切です。
最初から全て内製化しない
いきなり全業務を社内で完結させようとすると、人的リソースやスキルが不足し、施策がうまく回らずに頓挫するリスクがあります。
内製化は一気に進めるのではなく、社内で対応しやすい業務領域から段階的に取り組むことが成功の鍵です。
SNSの運用やアクセス解析など、小さな範囲から着手することで、徐々にノウハウと体制を構築できます。
また、段階的な移行を選ぶことで、業務ごとの難易度や課題を把握しやすくなり、適切な戦略修正も可能。
社員が実務を通じてスキルを習得する機会が増え、マーケティング全体の理解度も高まるでしょう。
人材やリソースの確保は余裕を持って準備する
内製化に必要な人材・スキル・時間を過小評価すると、プロジェクトが途中で停滞するリスクがあります。
具体的には、下記のような準備が求められます。
- 担当者の業務時間の確保
- 専門知識の教育・研修体制
- 必要なツール・環境の整備
余裕のある計画と、社内全体の理解・協力体制が重要です。無理のないスケジュール設計を意識しましょう。
部分的に専門人材を登用する
完全な内製化にこだわる必要はありません。
社内で対応しにくい部分や初期設計などは、フリーランスや専門会社に一時的に依頼することで、品質とスピードの両立が可能です。
例えば、
- 広告アカウントの初期設定を外部に依頼
- 月1回の戦略レビューを外部アドバイザーに委託
必要な箇所だけ外部人材を活用する「ハイブリッド運用」は、無理なく内製化を進める手法として有効と言えます。
ナレッジ共有・蓄積の仕組みを念入りに整える
WEBマーケティングを内製化する際に見落とされがちなのが、社内ナレッジの共有と蓄積の仕組みづくりです。
個々の担当者が属人的に業務を進めてしまうと、知見が組織内に残らず、担当交代時や新規施策の立ち上げ時に大きなロスが生じます。
情報をしっかりと記録・整理し、社内の誰でもアクセス・活用できる状態を保つことが、内製化を持続可能にする鍵です。
また、施策ごとの結果や改善点を体系的に記録することで、過去の失敗を繰り返さず、より精度の高いマーケティング戦略の立案につながります。
こうしたナレッジの循環が社内文化として根付けば、継続的に成果を出せるチームへと成長していくでしょう。
効率的に行うなら内製化支援サービスを利用するべき

WEBマーケティングを効率よく内製化するためには、経験豊富な支援サービスの活用が効果的です。
単なる運用代行ではなく、社内体制構築を目的とした伴走型のサポートを受けることで、スムーズな移行と成果の最大化が期待できるでしょう。
プロが最適な体制を提案してくれるから
内製化支援サービスを活用すれば、企業の現状や課題に合わせて最適なマーケティング体制を柔軟に設計してもらえます。
業種やターゲット、目標に応じた知見をもとに、業務の優先度や組織体制にフィットするスキル導入・分担を提案してもらえるため、自社に合った現実的な運用モデルを構築できます。
自社の強みや文化を生かしながら、段階的に運用力を高められるため、無理のないスムーズな内製体制の確立が可能になります。
採用支援も受けられるから
多くの内製化支援サービスでは、人材確保や育成に関する包括的なサポートを提供しています。
例えば、求めるスキルセットや経験を持った人材の紹介、募集要項の作成、面談アドバイスなどの採用支援に加え、既存社員向けの教育研修やOJT型サポートまで対応可能です。
体制強化に必要な人材を中長期的に安定して確保しやすくなるでしょう。
支援企業を採用面でもパートナーとすることで、リソース不足の不安を根本から解消できます。
時間とリソースを節約できるから
内製化は準備や仕組みづくりに多大な時間と労力を要しますが、支援サービスを活用すれば、初期構築や運用設計、必要ツールの選定、社員教育まで一貫して効率的に進められます。
自社のマーケティング担当者が迷う時間や手戻り作業を減らし、限られたリソースを最大限に活用できます。
社内で一から手探りで進める場合と比較して、失敗リスクを低減でき、成果に直結するスピーディな内製運用の立ち上げが実現可能です。
ソフトの選定や環境構築を担ってくれるから
マーケティングに必要なツールやシステムの選定・導入・運用設計は、専門知識が求められる領域です。
支援会社に依頼すれば、目的や体制に応じた最適なツール(広告配信、分析、CRMなど)の選定から、導入時の初期設定・社内トレーニング・業務フローへの組み込み支援まで一貫対応してくれます。
社内メンバーのITスキルや理解度に合わせた構築が可能になるため、誰もが使える運用環境が整い、マーケティング活動が社内で自走できる状態を早期に実現できるでしょう。
WEBマーケティングの内製化支援会社
株式会社デイワン

株式会社デイワンは、WEBマーケティングの内製化支援を得意とするパートナー企業です。
特徴は、計画策定だけでなく「社内で成果が出る運用体制」を構築するまでを、実践型で伴走支援する点にあります。
DX人材の育成や社内チームの立ち上げ、ツール環境の整備など、企業ごとの課題に応じて最適なプランを設計・実行。
自社で継続的に運用できる力を養いたい企業に最適です。
さらに、デイワンはブランディングやコンセプト設計、WEBサイト・動画・SNSコンテンツの制作まで、クリエイティブ領域にも対応。
ユーザー視点でのUI/UX設計を重視し、成果に直結するデジタル施策も併せて提供しています。
内製化のその先まで一貫して支援できる点が、他社にはない強みです。
まとめ|WEBマーケティングの内製化について
WEBマーケティングの内製化は、単なるコスト削減にとどまらず、企業の競争力強化やマーケティング精度の向上にもつながる有効な手段です。
外注依存から脱却し、自社にノウハウを蓄積することで、柔軟かつ迅速な施策運用が可能になります。
特に注目すべきポイントは以下の通りです。
- 外注コストや長期維持費の大幅削減
- お客様のニーズにスピード感を持って対応できる柔軟性
- 運用や改善の知見を社内に蓄積できる組織的メリット
- 外部パートナーとの調整負荷を減らし、効率的な業務運営が可能
近年は以下のような背景から、内製化を後押しする環境が整っています。
- AIや自動化ツールの発展で誰でも簡単に運用できる仕組みが増加
- 副業・フリーランスの活用による柔軟な外部連携
- YouTubeやUdemyなど、無料・低価格での学習機会の拡大
ただし、すべてを一気に社内化しようとせず、段階的に進めることが成功の鍵です。
- まずはSNS運用やアクセス解析など取り組みやすい業務から着手
- 必要なスキルや人材は、フリーランスや支援サービスで一部補完
- ナレッジ共有の仕組みを整えて属人化を防ぐことが重要
もし効率的かつ確実に進めたい場合は、内製化支援サービスの活用も視野に入れましょう。
ツールの選定や体制構築、人材確保から研修までを一貫して支援してくれるため、失敗リスクを最小限に抑えながら成果に近づけます。
内製化の第一歩を踏み出す準備ができたら、ぜひ専門家のサポートも活用して、理想のマーケティング体制を整えていきましょう。
本記事が、内製化を検討するきっかけや行動の後押しになれば幸いです。
この記事を書いた人
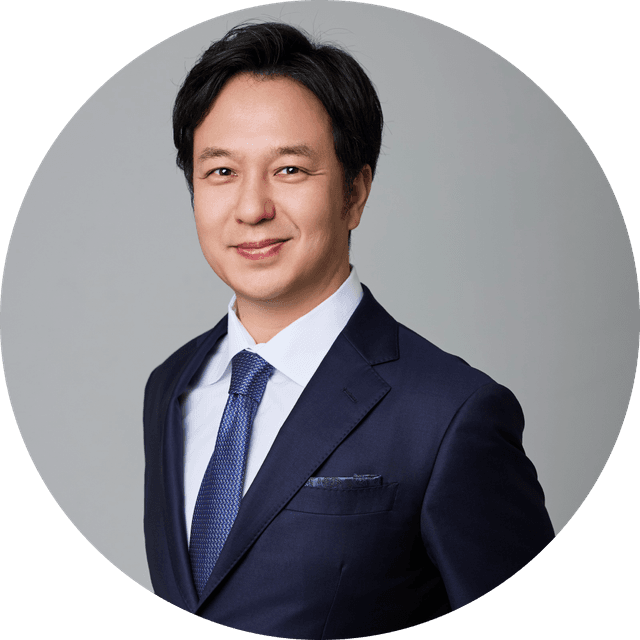
株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人
不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。


