creative
ホームページ制作
2025/07/17
【テンプレート】WEBサイト制作に必須のRFP(提案依頼書)の書き方
#bpo
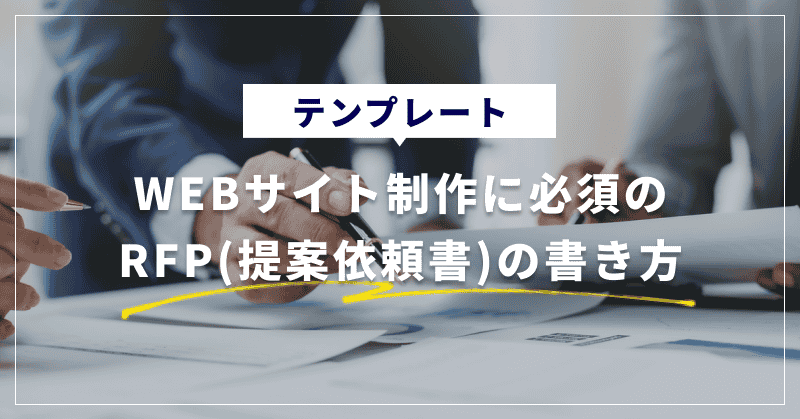
こんなことに悩んでいませんか? ・制作会社ごとに提案内容、金額がバラバラで、比較ができない ・要件をうまく伝えられず、追加費用や納期遅れのリスクが不安 ・RFPの書き方がわからず、作成にどれだけ時間がかかるか見えない 実は、無料テンプレートを使えば、1時間以内に高品質なRFPを作成できます。 この記事では、Webサイト制作・リニューアルに不可欠な「RFP(提案依頼書)」の書き方と無料テンプレートをご紹介します! この記事でわかること ・誰でも短時間で使えるRFPテンプレート(Excel形式)の構成と使い方 ・要件漏れ / 認識ズレ / 予算トラブルを防ぐ具体的な記載方法 ・発注後の運用保守を効率化する“内製+BPO”の最適解
目次
1.WEBサイト制作に必要なRFPのテンプレートを配布!
2.【テンプレート】WEBサイト制作のRFPの書き方5ステップ
2-1.目的・背景を端的に明示する
2-2.プロジェクト概要と現状課題を簡潔に書く
2-3.方針や要件をざっくり示す
2-4.提案希望内容を列挙
2-5.参考資料を添付する
3.RFP作成時に注意すべき項目と対策
3-1.目的|内容が曖昧
3-2.要件|優先度が不透明で意図しない設計に
3-3.参考資料|参考サイトの抜け漏れ
3-4.予算・スケジュール|レンジ提示が必須
4.WEBサイト制作後の運用保守は内製化すべき理由
4-1.スピーディーな更新業務
4-2.コミュニケーションコストの削減
4-3.嵩張りがちな外注費の削減
4-4.顧客や市場の変化に対応しやすい
5.WEBサイトの運用保守にはBPOを用いた内製化がおすすめ
5-1.属人性が低い運用が可能
5-2.リソースの無駄がない
5-3.トラブル対応がスムーズ
6.WEBサイトの運用保守なら「デジえもん」がおすすめ
7.まとめ|WEBサイト制作に必要なRFPテンプレートを配布
WEBサイト制作に必要なRFPのテンプレートを配布!
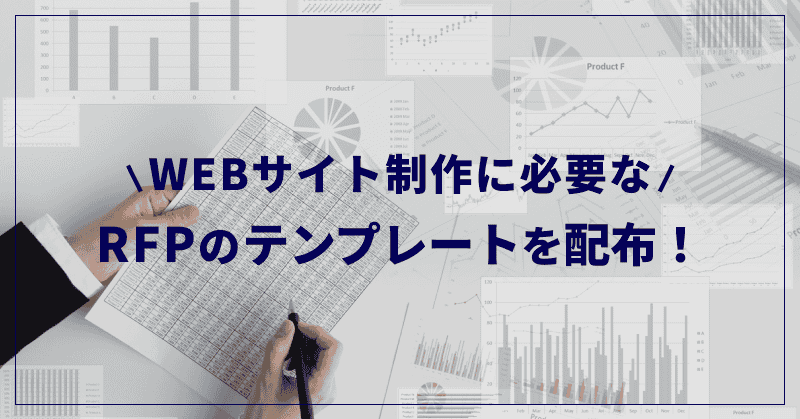
Webサイト制作・リニューアルを外部発注する際に、発注者側でRFP(提案依頼書)を準備していないと、見積条件の比較が難航し、ベンダー選定や稟議承認で混乱を招きます。
特に、要件の曖昧さや説明不足が原因で「追加費用が発生する」「納期が遅れる」といったトラブルも多発しています。
こうした背景から、誰でも短時間で必要項目を網羅できるRFPテンプレートをご用意しました。
テンプレートは「目的・背景」「プロジェクト概要」「要望項目」「納期や予算条件」などを項目別に整理しており、制作会社やフリーランスとの商談前に簡単にカスタマイズ可能です。
【テンプレート】WEBサイト制作のRFPの書き方5ステップ
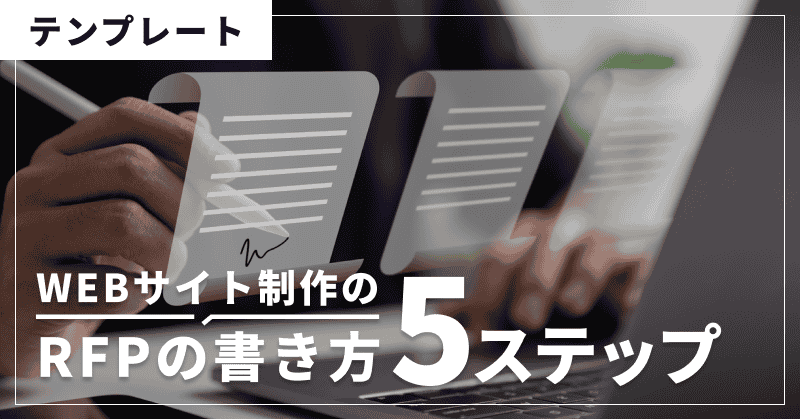
RFP(提案依頼書)の目的は、Webサイト制作における要望や条件を明文化し、ベンダー選定や見積比較を円滑に進めることです。
とはいえ、社内にWeb担当者がいない企業にとっては、何をどの順序で書けばよいのか判断が難しいのも事実です。
そこで以下では、誰でも漏れなく要件を伝えられるよう「5つの基本構成」に整理して解説します。
- ・目的・背景を端的に明示する
- ・プロジェクト概要と現状課題を簡潔に書く
- ・方針や要件をざっくり示す
- ・提案希望内容を列挙
- ・参考資料を添付する
目的・背景を端的に明示する
まず最初に、Webサイトを制作・リニューアルする目的と背景を端的にまとめましょう。
ここで重要なのは、「なぜ今このタイミングでWebサイトが必要なのか?」を経営目線で言語化することです。
たとえば、「展示会出展にあわせて製品ページを強化したい」「会社ロゴ刷新に伴い、ブランド認知度を高めたい」など、プロジェクトのきっかけと目標をセットで記載します。
あくまで提案依頼書なので、1〜3行で完結させるのが理想です。
プロジェクト概要と現状課題を簡潔に書く
次に、現在のWebサイトの状況や抱えている課題を整理します。
詳細なデータは別添資料とし、本文では以下のように箇条書きでシンプルに記載しましょう。
- ・ページ数:約25P(CMSあり)
- ・主な流入経路:自然検索+名刺経由
- ・主な課題:スマホ未対応、問い合わせ数が月2件未満、更新が属人化しており情報が古い
上記のように、定量的・定性的な情報を混ぜることで、ベンダー側の理解が深まります。
方針や要件をざっくり示す
RFPでは、詳細な機能設計を決める必要はありません。
むしろ「必要だと考えている要件」や「方針の方向性」をざっくり伝える程度で十分です。
区分 | 要件内容 |
Must要件 | レスポンシブ対応/SSL/フォーム設置 |
Want要件 | 多言語対応/MA連携 |
納期希望 | 2026年3月末 |
予算目安 | 300〜500万円 |
このようにレンジで伝えることで、見積もり比較や社内承認がスムーズになります。
提案希望内容を列挙
ベンダーに対してどんな提案を求めているかを明示することで、的外れな内容を避けられます。
以下のように、依頼内容を具体的に箇条書きしましょう。
- ・Webサイトの構成案と情報設計
- ・デザインコンセプトと参考デザインの提示
- ・更新体制の提案(CMS or 外注案)
- ・見積書(機能別・ページ別内訳)
必要であれば、今後の運用保守や効果測定(KPI)についての方針も提示すると、長期的視点の提案が得られやすくなります。
参考資料を添付する
提案の精度を高めてもらうために、以下のような参考資料を添付しましょう。
特に現状サイトのアクセス状況や競合ベンチマークは、提案に直結します。
- 会社案内・沿革・組織図(PDF)
- 現在のサイト構成図
- ベンチマークサイトURL(3社程度)
- 過去の施策レポート(あれば)
適切な参考資料の共有は、提案の質だけでなく納期の短縮にもつながります。
RFP作成時に注意すべき項目と対策
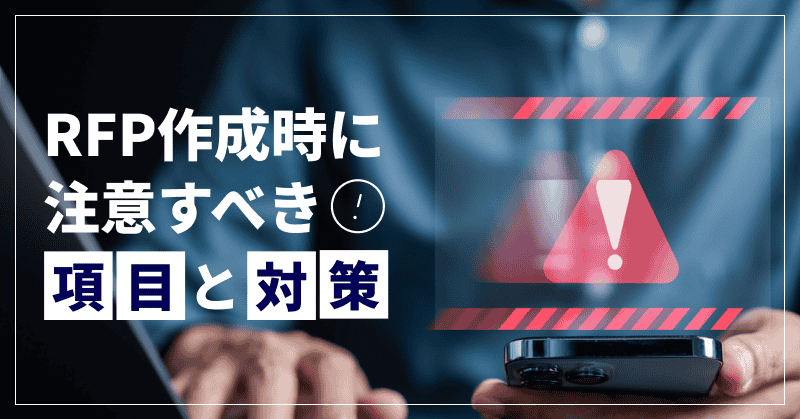
RFP(提案依頼書)は、記載内容の精度がそのままプロジェクトの成否に直結します。
とくにWebサイト制作では、目的や要件の伝達ミス、参考資料の不足、曖昧な予算感が原因で「意図しない設計」「不必要な機能実装」「想定外の追加費用」といった問題が頻発します。
以下では、実務でよくある失敗とその対策を具体的に解説します。
目的|内容が曖昧
RFPで「目的」が曖昧だと、ベンダーの提案が的を外れたものになりやすく、見積もり内容もバラバラになります。
失敗例としてよくあるのが、「サイトをきれいにしたい」といった漠然とした表現。
これでは構成も機能要件もブレてしまい、判断基準が定まらなくなります。
できれば、「年間商談数を1.5倍に」「応募数を月20件確保したい」といった具体的な数値KPIを明示しましょう。
また、プロジェクトスコープも併せて記載するのが重要です。
例えば、「トップページ含む新規5ページの作成+WordPress導入」といった具合に、制作範囲を数量ベースで表現すると、ベンダー側とのズレが大幅に減ります。
要件|優先度が不透明で意図しない設計に
要件定義において、機能や仕様の「優先度」が曖昧だと、制作会社は安全側に倒しがちになり、結果として工数オーバーや不要な設計につながります。
たとえば、MAツール連携や多言語対応を「つけてもいい」と曖昧に伝えると、それを前提に見積もられてしまうことがあります。
その対策として、以下のように「MUST/WANT」で要件を分類する方法が有効です。
優先度 | 要件内容 |
MUST | SSL対応、レスポンシブ対応、フォーム設置など |
WANT | MA連携、多言語対応、アクセス解析機能 |
このように優先度を明確にすると、設計の方向性が一致し、不要な追加機能を防げます。
要件をすべて列挙したうえで、取捨選択の余地を設けることが、結果的にコスト最適化にもつながります。
参考資料|参考サイトの抜け漏れ
デザインの方向性を明示せずに発注を進めると、「イメージと違う」となるケースが非常に多く、制作工程での手戻りにつながります。
特にWebサイトのUI/UXやトンマナは文章では伝わりづらいため、参考サイトの提示は必須といえます。
デザインは“視覚で伝える情報設計”です。
URLやスクリーンショットを添付し、言葉で補足する形が最も効果的です。
予算・スケジュール|レンジ提示が必須
予算とスケジュールを明記しないと、ベンダーごとに金額や納期感が大きく異なり、比較検討が難しくなります。
さらに、要望が膨らむたびに再見積もりが必要となり、社内承認やプロジェクト開始が後ろ倒しになるケースも多発します。
失敗例でよくあるのは、「予算未定」「納期も柔軟に対応」といった記載。
これではベンダー側も基準を持てず、かえって手戻りが発生しやすくなります。
以下のようにレンジで伝えるのが最適です。
項目 | 提示内容 |
予算 | 300〜500万円 |
納期希望 | 2026年3月末までに公開希望 |
こうした「幅のある提示」が、見積もりの精度とスピードを高めます。
プロジェクト開始前に予算と公開時期の目安を必ず明文化しておきましょう。
WEBサイト制作後の運用保守は内製化すべき理由

WEBサイトは「作って終わり」ではなく、「運用フェーズ」で成果を最大化できるかが分かれ目になります。
更新作業や保守管理を外注し続けると、コストは膨らみ、対応スピードも落ち、チャンスを逃すことも。
そこで重要なのが、RFP段階から「運用を見据えた内製化の仕組み」を設計しておくことです。
スピーディーな更新業務
運用フェーズで最も差が出るのが「更新スピード」です。
Webサイトを内製化しておけば、社内の担当者が即日で更新・修正対応を行えるため、情報鮮度が落ちるリスクを回避できます。
とくにキャンペーン情報や製品ニュースなど、日々の発信が重要な企業ではその恩恵は非常に大きいです。
- キャンペーン情報の差し替えが即日可能
- 営業からのフィードバックを即座に反映
- 軽微な画像・文言修正も最短5分で対応
スピードは競争力です。
更新を待つのではなく、動ける体制を持つことが成果直結の第一歩です。
コミュニケーションコストの削減
内製化によって外部パートナーとのやりとりが減ると、想像以上に“無駄な時間と工数”が削減されます。
修正内容を伝えるための資料づくり、意図のズレによる手戻り、納期調整のストレス…これらはすべて社内完結なら不要です。
削減できる典型的なやりとり
- 修正指示のドキュメント化/打ち合わせ
- 再確認・再修正の往復
- スケジュールや費用の交渉調整
情報伝達コストを省き、意思決定と更新作業を直結させる体制こそが、スピードと精度を両立させる鍵となります。
嵩張りがちな外注費の削減
Webサイトの保守・更新を外注する場合、小さな作業でも費用が積み上がりやすく、予算を圧迫する原因になります。
以下は代表的な費用相場です。
作業項目 | 外注費用目安 |
トップページのビジュアル更新 | 10万〜30万円 |
下層ページの新規追加(1P) | 2万円〜5万円 |
テキスト・画像差し替え | 5,000円〜 |
このような軽微な更新作業を社内で完結できれば、外注依頼のたびにかかる費用を大幅に抑制可能。
年間で数十万円、場合によっては100万円超のコスト圧縮が実現できます。
顧客や市場の変化に対応しやすい
Web運用の内製化により、顧客の反応や市場トレンドに対して柔軟かつ迅速に対応できます。
たとえば、営業現場で拾ったニーズを即日コンテンツに反映したり、検索トレンドに沿ったキーワードでページを更新したりと、マーケティング活動との連携が格段に高まります。
内製体制でできる対応例
- 商談中の質問に基づくFAQ追加
- 想定外のクレームに即対応したLP修正
- 季節や時流に応じたCTA変更や特設ページ制作
この“変化への即応性”は、競合との差別化を生み出す重要な強みです。
更新の速さは、顧客との距離を縮める手段でもあります。
WEBサイトの運用保守にはBPOを用いた内製化がおすすめ

WEBサイトの運用フェーズでは「更新スピード」「柔軟性」「安定した体制」が成果に直結します。
とはいえ、完全な社内体制をゼロから構築するのは現実的ではありません。
そこで有効なのがBPOサービスです。
BPOを活用すれば、属人性の排除・コスト効率・緊急時対応といった課題をまとめて解消できます。
以下では、なぜBPOが有効か、3つの観点から解説します。
属人性が低い運用が可能
代理店以外で外部のサポートを頼る場合、フリーランス人材を活用するという手段もあります。
しかし、フリーランス契約は人単位での対応になるため、担当者の体調不良や案件過多で業務が止まるリスクがあります。
一方、BPOサービスは複数名体制かつマニュアルベースで運用されており、誰が抜けても保守・更新業務が継続可能です。
比較項目 | フリーランス | BPOサービス |
担当者変更の影響 | 作業が停止するリスクあり | 引き継ぎ体制あり、業務が継続される |
作業管理 | 個人の裁量・経験に依存 | マニュアル+進行管理ツールで標準化 |
サポート体制 | 1名対応が基本 | 複数名体制で不在時も対応可能 |
属人性を排除し、業務を安定的に継続させたいなら、BPOを使った内製化が最も合理的な選択肢といえます。
リソースの無駄がない
従来の保守契約では、「作業がなくても費用が発生」「内容変更に都度見積もりが必要」など、コストパフォーマンスに課題がありました。
BPO型なら、未使用リソースを柔軟に別業務に転用でき、支払った費用が無駄になりません。
契約モデル | 未使用リソースの扱い例 |
一般的な保守契約 | 作業がゼロでも費用発生/修正は都度見積もり |
BPOサービス | SNS運用・レポート作成・SEO施策などへ転用可能 |
例えば「更新作業が少なかった月」は、余剰時間をLP改善やバナー制作に充てるといった柔軟な運用が可能になります。
「費用を払ったけど何もされてない」を防ぐには、BPOのような再配分型の契約モデルが有効です。
トラブル対応がスムーズ
サーバー障害やフォームの不具合など、WEBサイトの運用では突発的なトラブルがつきものです。
フリーランスや制作会社では平日9〜18時対応が中心で、夜間や休日は対応できないこともあります。
BPOサービスであれば、SLA(サービス品質保証契約)付きの夜間・休日対応がオプションで付属。
誰が・どの範囲を・いつまでに対応するかが契約に明記されており、緊急時も安心です。
- 夜間・休日の障害時対応が可能
- トラブル時の対応フローを事前に契約で明文化
- チャット・電話・メールなど複数の連絡手段を確保
緊急時にあたふたせず、速やかに修復対応できる体制を整えるには、BPO型の保守体制が最適解といえるでしょう。
WEBサイトの運用保守なら「デジえもん」がおすすめ
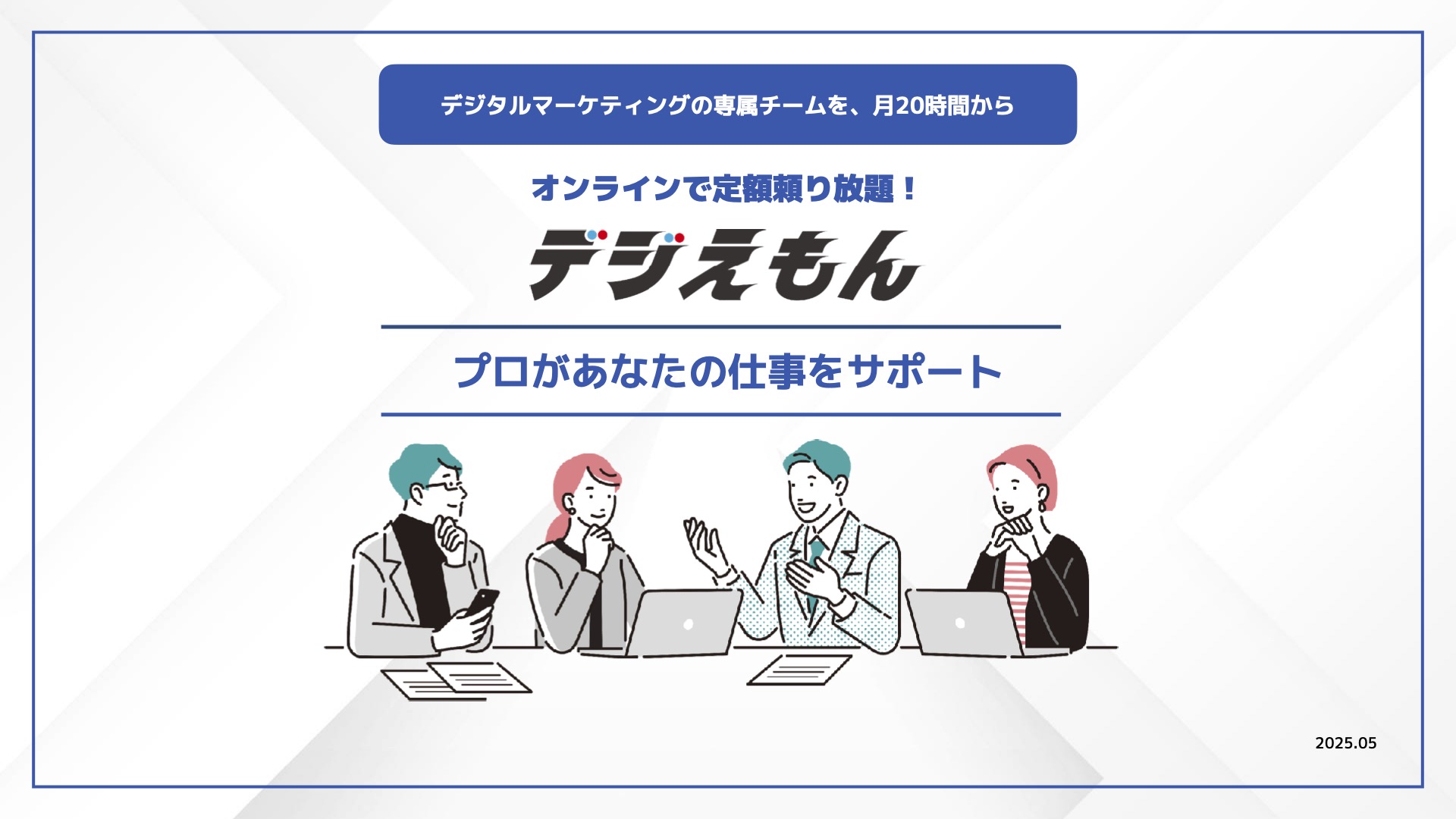
Web業務に強いBPOをお探しなら、Web・IT業務に特化した「デジえもん」がおすすめです。
一般的なBPOは経理や事務などの業務が中心ですが、デジえもんはWeb制作・マーケティング・システム運用など、専門性の高いデジタル業務に対応可能。
デザイナー・エンジニア・マーケターといったプロ人材がチームで稼働し、ホームページの更新・保守から、バナー制作・広告運用・GAレポート作成まで一気通貫で対応します。
契約は最低月20時間からスタート可能で、余った稼働時間は別業務への転用もOK。
保守だけにとどまらず「ちょっと困った社内の業務」もまとめてアウトソースできます。
フリーランスより安定性が高く、制作会社よりコスト効率に優れるBPOモデルとして、定型業務からマーケティング改善まで柔軟に対応します。
業務カテゴリ | 対応業務例 |
Webサイト保守・更新 | ホームページ修正、WordPress管理、サーバー保守、フォーム改修など |
クリエイティブ業務 | HTML/CSSコーディング、ホワイトペーパー制作、動画編集、記事ライティング、翻訳対応など |
マーケティング業務 | SEO管理、広告運用(Google/Yahoo/SNS)、GAレポート作成、メルマガ配信支援など |
SNS運用・代行 | 投稿素材作成、予約投稿、コメント返信代行、競合リサーチなど |
その他IT業務支援 | CRM導入支援、マニュアル整備、SaaS初期設定、一次チャット対応など |
「誰に頼めばいいか分からない」「兼任でまわらない」と感じたら、まずはデジえもんの資料をご確認ください。
まとめ|WEBサイト制作に必要なRFPテンプレートを配布
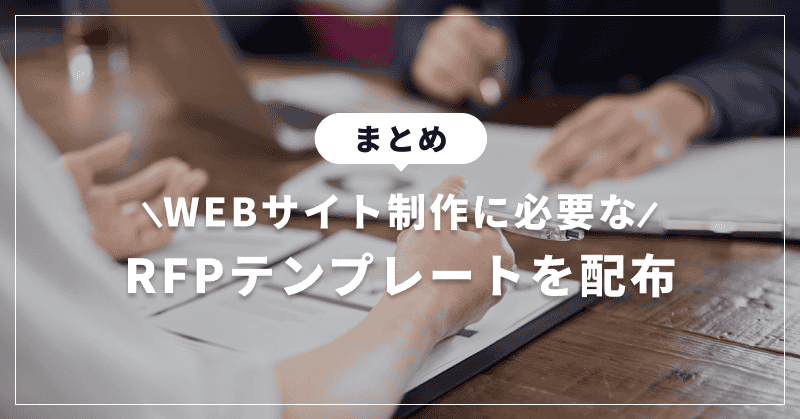
Webサイト制作で成果を出すためには、「RFPの質」と「運用体制の設計」がすべての出発点です。
以下の観点を押さえることで、ベンダー選定・見積比較・納期管理・運用保守まで一貫してスムーズに進行できます。
効果的なRFP作成のポイント
- 「目的・背景」を数値KPIで明記し、判断基準を明確に
- 要件はMUST/WANTで分類し、不要な工数を防止
- 提案希望内容を箇条書きで具体的に列挙
- デザイン方針や仕様はビジュアルで共有
- 予算・納期はレンジで記載し、見積精度を向上
よくあるRFPの失敗とその対策
- 目的が曖昧 → KPIと制作スコープで明文化
- 要件の優先度が不明 → 機能要件を分類して提示
- 参考資料の不足 → 競合サイトや現状図を添付
- 予算未提示 → 社内承認もベンダー比較も不利に
運用保守は内製+BPOのハイブリッドが最適解
- 更新スピードが向上し、顧客接点が即時で強化
- コミュニケーションロスがなく、精度と速度を両立
- 外注コストを圧縮し、マーケティング投資へ再配分可能
- 市場変化に柔軟対応でき、競争力が持続
- 属人性を排除し、夜間トラブルも安心のBPO体制を構築
「デジえもん」ならWeb業務に完全対応
- サイト保守からSNS運用、広告・SEO対策まで一気通貫
- 余剰リソースは別業務に柔軟転用可能
- 月20時間から導入でき、コストも明快
- フリーランスより安定、制作会社より柔軟な体制を実現
RFPの設計と運用体制の整備は、Web施策の成果を左右する“起点”です。
この記事で得たヒントを、貴社のプロジェクト成功にぜひご活用ください。
この記事を書いた人
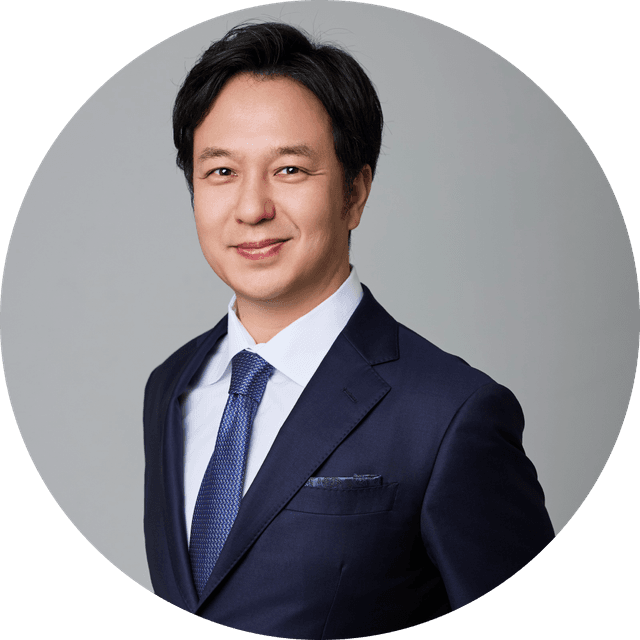
株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人
不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。


