in-house
DX
2025/04/06
企業のIT業務を内製化するメリットや手順を解説!低リスクで進めるポイントも紹介します
#in-house #bpo #dx
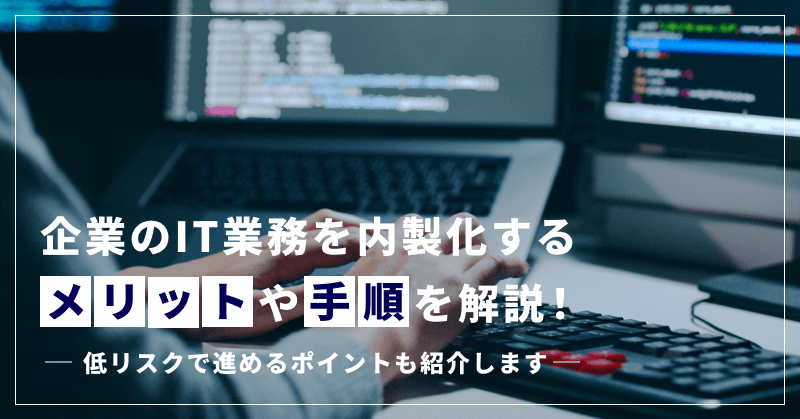
目次
1.企業がIT人材の育成や内製化を進めるメリット
1-1.柔軟かつスピーディーな対応が可能になる
1-2.外注コストの削減
1-3.ノウハウの蓄積
1-4.コミュニケーションが取りやすい
2.企業がITの内製化を進める際の課題やデメリット
2-1.育成・採用コストがかかる
2-2.体制作りが難しい
2-3.システムの初期費用が発生する
2-4.生産性や品質が落ちる可能性がある
2-5.費用が不明確、意識が希薄になる
3.IT内製化を進める手順
3-1.外注内容や状況の可視化
3-2.内製化の目的・対象箇所の明確化
3-3.必要なリソースの明確化と確保
3-4.徐々に外注範囲を減らす
3-5.完全に外注を減らし内製する
4.リスクを抑えてITの内製化を進める方法やポイント
5.IT内製化支援サービスを展開するおすすめ企業3選
5-1.株式会社デイワン
5-2.株式会社メンバーズ
5-3.バクリ株式会社
6.ITの内製化支援企業の選定基準
7.IT内製化の企業事例
7-1.株式会社西日本シティ銀行
7-2.ジヤトコ株式会社
8.まとめ|IT業務の内製化をする企業メリット
「『IT業務の内製化』と聞いても、何から手をつければいいのか分からない...」
そんなお悩みをお持ちではないでしょうか。
外注に頼りきりで柔軟な対応ができなかったり、社内の兼任スタッフに限界を感じていたりする企業は少なくありません。
とはいえ、フルタイム人材の確保や大規模な組織改編はリスクが高いと感じるのも自然なことです。
実は、今は副業人材や業務委託などを活用し、小さくリスクを抑えて始めることが可能です。
この記事では、IT内製化のメリット・課題・進め方をわかりやすく解説しながら、何から考えればいいか分からない状態から一歩踏み出すヒントをお届けします。
また、内製化の進め方や重要なポイントを実際の成功事例を元に解説したお役立ち資料もぜひダウンロードください。
企業がIT人材の育成や内製化を進めるメリット

企業がIT業務の内製化を進めることで、ビジネス環境の変化に対し柔軟かつスピーディーに対応できる体制が整います。
外注コストの削減やノウハウの蓄積といったコスト面・成長面のメリットも大きく、社内でのコミュニケーションも円滑になるでしょう。
以下で具体的なポイントを解説します。
柔軟かつスピーディーな対応が可能になる
社内でIT人材を確保することで、外部委託よりも遥かにスピーディーな対応が可能になります。
外注の場合、まず自社の業務背景や目的を共有する必要があり、その段階で情報共有や説明に多くの時間と労力を費やすことになるでしょう。
また、外注先は他のクライアントの案件も抱えており、自社の案件を常に優先してもらえるとは限りません。
結果として、変更対応や追加施策の実行が遅れるリスクが高まります。
一方で、内製化されたチームであれば業務知識も蓄積されており、変化に迅速に対応できる柔軟性を持つことができます。
とくに、デジタル施策をスピーディーに展開したい企業にとっては、大きな競争力となるでしょう。
外注コストの削減
IT業務を外部の制作会社やベンダーに依頼すると、実作業にかかる費用だけでなく、管理費やディレクション費用などの間接コストも発生します。
これらが積み重なることで、実際の成果以上に高いコストがかかるケースも少なくありません。
内製化を進めることで、こうした間接コストの削減が可能です。
また、継続的な運用業務についても、社内で実施できればスピードと品質を両立しつつ、コスト最適化が実現できるでしょう。
すべてを内製化するのが難しい場合も、一部の業務から着手することで段階的なコスト削減が可能です。
ノウハウの蓄積
IT業務を内製化することで、施策の
- 企画
- 設計
- 実行
- 改善
という一連のプロセスを社内で管理できるようになります。
ノウハウや技術力が社内に蓄積され、継続的な改善サイクルが実現しやすくなるでしょう。
例えば、広告運用ではABテストを繰り返し効果が高い運用方法を実現するべきですが、社内と外注ではスピード感が全く違います。
高頻度でお願いする場合はより一層コストがかかるでしょう。
また、CMSの運用やWebサイトの分析・改修も、内製化によりスピーディーかつ戦略的に進められます。
蓄積されたノウハウは、次なる施策やプロジェクトに即応できる武器となり、将来的にも大きな資産になるはずです。
コミュニケーションが取りやすい
外注先へのよくある不満が「返信が遅い」「意思疎通に時間がかかる」といったコミュニケーションの課題です。
特に、期日が決まっているキャンペーンや重要なプロジェクトでは、スピーディーな意思決定と実行が求められます。
内製化されたチームであれば、同じ社内にいるため意図の伝達やフィードバックのスピードが段違いに向上します。
また、チャットツールやプロジェクト管理ツールを用いたリアルタイムな情報共有も可能になり、業務全体のスピードと精度が格段に向上するでしょう。
コミュニケーションの改善は、結果として施策の成功率にも直結します。
企業がITの内製化を進める際の課題やデメリット
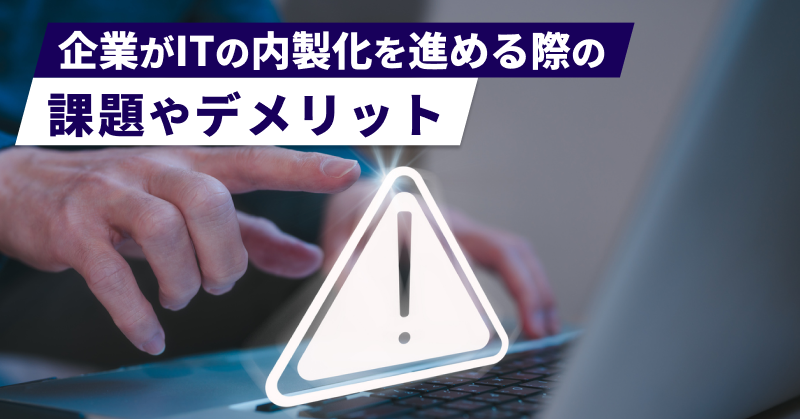
IT業務の内製化には多くのメリットがありますが、同時にいくつかのハードルやリスクも存在します。
特に「人材不足」「ノウハウの欠如」「体制構築の難しさ」など、準備段階での負担が大きく、スムーズな推進が困難になることもあります。
育成・採用コストがかかる
IT人材を自社内で確保・育成するには、時間もコストもかかります。
エンジニアやデザイナーといった専門職は市場でも人材不足が続いており、採用競争が激化。
採用後に社内での研修や実務経験を積ませるには、数ヶ月〜1年単位の投資が必要でしょう。
その間、業務の推進速度が落ちてしまうリスクも考慮しなければなりません。
しかし近年では、副業人材や業務委託といった柔軟な働き方も普及しており、必ずしもフルタイムの正社員を前提にしなくてもIT内製化の第一歩を踏み出すことができます。
小さく始めるという戦略が、今後の企業成長を支える鍵となるでしょう。
体制作りが難しい
ITの内製化は、単なる人材の確保だけでなく、組織全体の理解と協力が求められます。
システム部門だけが内製化を進めようとしても、営業部門やマーケティング部門など他部署との連携が不十分であれば、施策はスムーズに進みません。
特に中小企業では、リソースが限られているため、横断的な体制を構築すること自体が難しくなる傾向にあります。
加えて、現場が「外注のほうが楽だ」という意識を持っていると、内製化への協力が得られにくくなるケースもあります。
なぜ内製化が必要なのかを全社的に共有し、組織全体で推進する土壌を作ることが大切です。
システムの初期費用が発生する
内製化に取り組む際には、ツールやシステムの導入に伴う初期費用が発生する場合があります。
特にCMSや業務支援ツール、プロジェクト管理ソフトなど、用途に応じて必要な基盤を構築しなければなりません。
しかし最近では、SaaSやサブスクリプション型のクラウドサービスが主流となっており、従来のように高額な初期投資を必要としない選択肢も増えています。
ツールの選定次第で、初期費用の負担は大きく変動するため、慎重な見極めが必要です。
生産性や品質が落ちる可能性がある
IT業務を社内で兼任体制のまま進めた場合、既存業務とのバランスが崩れ、生産性が低下するリスクがあります。
例えば、本来は経理や総務を担当しているスタッフにWeb更新や簡易的な開発作業を任せると、それぞれの業務のパフォーマンスが落ちてしまいます。
クリエイティブ領域の作業を非専門人材に任せてしまうと、クオリティの低下を招きかねません。
特にWebデザインやコンテンツ設計はユーザー体験に直結するため、一定レベル以上の品質が求められます。
こうしたリスクを回避するためにも、兼任ではなく専任の人材を用意するか、しっかりと工数を用意する必要があります。
費用が不明確、意識が希薄になる
外注費用は見積書などで明確化しやすい一方、内製化は人的コストや工数の把握が難しくなりがちです。
社内の人件費に含まれてしまうため、プロジェクトごとの費用対効果が可視化されず、リソース配分や改善の判断が遅れる原因になります。
さらに、「内製だからコストはかかっていない」という錯覚が生じると、作業工数が増えても見直しの機会を逃す恐れがあります。
タスクごとの時間管理や業務日報などを活用し、可視化と評価の仕組みを整えることが大切です。
適切な工数管理ができていなければ、内製化がかえって非効率を招くでしょう。
IT内製化を進める手順

- 外注内容や状況の可視化
- 内製化の目的・対象箇所の明確化
- 必要なリソースの明確化と確保
- 徐々に外注範囲を減らす
- 完全に外注を減らし内製する
外注内容や状況の可視化
まず取り組むべきは、現在外部委託している業務やプロジェクト内容の棚卸しです。
「どの業務を、どれだけの費用で委託しているか」を正確に把握することが重要です。
ここで得られる情報は、内製化の対象選定や優先順位付けにおける基礎データになります。
また、外注依存が強い領域や、属人化している業務があれば注意が必要です。
内製化によるリスクや工数が大きくなる可能性があるため、最初の段階で整理しておきましょう。
業務プロセスを可視化することで、必要なスキルや工数、リソースも見えやすくなります。
現状把握なくして、正しい内製化の戦略は立てられません。
内製化の目的・対象箇所の明確化
内製化は「何のために行うのか」を明確にすることが成功の鍵です。
コスト削減、スピード向上、ノウハウ蓄積、セキュリティ強化など、目的によって進め方や優先順位が変わります。
加えて、どの業務を内製するかも明確に決める必要があります。
例えば、Webコンテンツ運用やSNS発信、分析レポート作成などは内製化しやすい領域です。
一方で、基幹システムの再構築など高度な技術が必要な領域は、外部パートナーとの連携を続けながら進めるのが現実的です。
目的と対象を曖昧なまま進めると、成果が見えづらくなり、内製化の効果が感じられなくなる可能性もあるため、最初にしっかりと定義しておきましょう。
必要なリソースの明確化と確保
内製化に必要なリソースとは、単に人数だけではなく「どのようなスキルセットが、どのタイミングで必要か」という点も含まれます。
特にエンジニアやデザイナー、マーケティング担当など、役割ごとに必要な人材像を整理することが重要です。
すべての人材を正社員で賄う必要はありません。
近年では、副業人材やフリーランス、業務委託など、多様な働き方を選べる人材も増えており、優秀な人材を柔軟に確保できる環境が整いつつあります。
スモールスタートで段階的にチームを拡大することで、コストや教育負担を抑えつつ、確実に体制を整えることが可能です。
そういった人材と自社の正社員とのハイブリッドで進めるのも選択肢の一つです。
徐々に外注範囲を減らす
内製化を一気に進めるのではなく、段階的に外注依存を減らすアプローチが現実的です。
例えば、まずは運用業務のうち一部だけを内製化し、社内メンバーが業務フローや成果物に慣れる時間を確保します。
次に、成果や課題を振り返りながら、さらに広い範囲へと内製化を拡大していきます。
段階的に進めることで、社内のスキルレベルや課題に応じた柔軟な対応が可能となり、リスクも最小限に抑えられるでしょう。
進捗に応じて必要な研修や外部サポートを活用することで、スムーズな移行が実現します。
内製化は、いきなり全てを自社で完結させるのではなく、フェーズを分けて着実に進めていくことが成功のポイントです。
完全に外注を減らし内製する
最終段階では、可能な範囲で外注依存を減らし、業務の大部分を自社で完結できる体制へと移行します。
このとき重要なのは、単に人材を揃えるだけでなく、業務プロセスの最適化と運用フローの整備です。
内製化した業務の成果を定量的に測定し、継続的に改善していくPDCAサイクルを社内で回せるようになることが理想と言えます。
とはいえ、すべてを完全に自社で抱える必要はなく、専門性の高い部分は引き続き外部パートナーを活用するなど、柔軟な判断も必要です。
重要なのは「選べる状況」を作ること。
外注と内製の最適なバランスを見極め、自社の成長にあわせて継続的に体制をアップデートしていきましょう。
リスクを抑えてITの内製化を進める方法やポイント
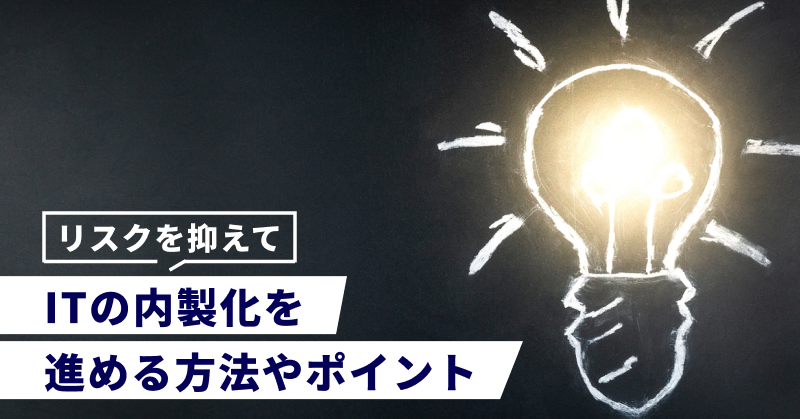
IT内製化を低リスクで進めるためには、社員への教育と適性の見極めがカギになります。
特にDXやクラウドなど最新のIT技術に関する基礎知識は、エンジニア職でなくとも身につけるべき領域です。
一般社員を対象とした研修やeラーニングの導入を通じて、全社的なリテラシーを底上げしておくことで、内製化の障壁はぐっと下がるでしょう。
その中でも特に理解力があり、柔軟な対応ができる社員を内製化プロジェクトの中心メンバーに据えることで、初期の混乱や失敗を防ぐことが可能です。
また、副業や業務委託といった外部リソースと社内メンバーのハイブリッド体制を組むことで、技術的なギャップを埋めつつ徐々に自走できる環境を整備できます。
社内教育と適性配置は、最も重要なリスクマネジメント施策の一つです。
IT内製化支援サービスを展開するおすすめ企業3選
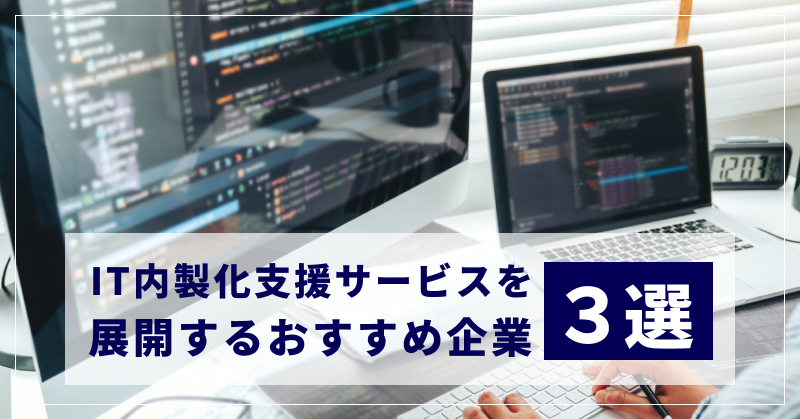
株式会社デイワン
株式会社デイワンは、企業のIT内製化を“伴走型”で支援する専門企業です。
検討段階からハンズオンで関与し、
- 計画立案
- 体制作り
- 採用支援
- 人材育成
- ツール導入
に至るまで、実行可能なプロセスを一貫してサポートします。
特に「自社の価値をデジタルでもっと強くしたい」という企業の想いに寄り添い、丁寧なヒアリングと現場密着型の支援を通じて、最適な内製化戦略を提案いたします。
加えて、リスクを最小限に抑えるための進め方や段階的な導入方法も提案させていただくため、「何から始めればいいかわからない」「体制が整っていない」といった企業でも安心して取り組めます。
短期的な成果だけでなく、社内にノウハウを蓄積し、将来的に外部依存から脱却できる体制づくりを目指す方はぜひお問い合わせください。
株式会社メンバーズ
株式会社メンバーズは、Web運用や広告運用などのデジタル業務を内製化するための支援に強みを持つ企業です。
特徴は、クライアントと「一体化」し、まるで社員のように伴走する支援体制。
デジタル人材を専任チームとして提供し、業務プロセス改善や生産性向上、PDCAの高速化など、現場レベルでのDX推進を実現します。
準インハウス型から完全インハウス型まで、企業ごとの理想に合わせた柔軟な支援が可能で、広告運用・Webサイト運営に関しても、ノウハウやマニュアル整備・リスキリング支援を通して、組織にスキルを残す仕組みを構築。
1,000社以上の現場支援で得た知見を活かし、「戦略よりも実行」を重視した実務支援に定評があります。
業務属人化の解消や成果重視の内製化を目指す企業にとって、実践力のあるパートナーと言えるでしょう。
バクリ株式会社
バクリ株式会社は、広告運用やWeb戦略に課題を感じている企業に向けて、実行力に直結するIT内製化支援を展開しています。
特に、準大手企業(業界3〜10番手)や中小企業で「これからWebに注力したい」と考えている経営層・部門長にとって、頼れるパートナーです。
広告運用・SEO・データ分析・クリエイティブ制作・ツール導入まで、Webマーケティング全体を対象にした支援が可能で、社内にノウハウを残す体制構築に注力。
内製化によって外注コストの削減と意思決定の迅速化を両立し、成果につながるインハウス体制を実現します。
また、教育・トレーニングによってスキルを定着させるため、社内人材のレベルアップにも貢献。
Web戦略に不安を抱える企業にとって、伴走型で成果を出せる実践的な支援が受けられる点が大きな魅力と言えるでしょう。
ITの内製化支援企業の選定基準
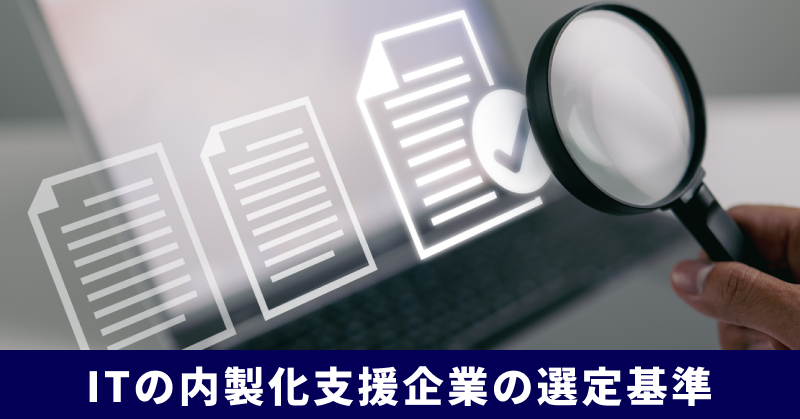
ITの内製化支援企業を選定する際は、単なる技術力の高さだけでなく、自社の業務やビジネスモデルへの理解度が深いかどうかが重要な判断基準となります。
特に、課題整理から体制作り・育成計画・運用までを一貫してサポートできるかを見極めることが大切です。
また、伴走型で現場に寄り添い、継続的なスキル移転やノウハウの蓄積を促してくれる企業であれば、将来的な自走体制の構築につながります。
さらに、クラウドやDX推進、ローコード/ノーコードツールなどの最新トレンドに柔軟に対応できるかも評価ポイントです。
自社の段階に合った支援が可能かどうかを見極めたうえで、信頼できるパートナーを選びましょう。
IT内製化の企業事例

株式会社西日本シティ銀行
株式会社西日本シティ銀行では、デジタル広告の内製化により広告費を40%削減しつつ、ローン申込件数を1.6倍に伸ばす成果を実現しました。
外部代理店に頼っていた従来の運用体制から、自行内にノウハウを蓄積できる体制へとシフトしたことで、改善サイクルの高速化と広告品質の向上を同時に達成。
行員が中心となり運用を行い、パートナー企業と連携した共創体制を構築しています。
ターゲット設計からクリエイティブの改善、さらに生成AIの活用による工数削減までを組み合わせることで、PDCAを効率よく回し、ROI向上にも貢献しました。
継続的に成果を出すためには、社内の運用力を高める内製化が有効な選択肢であることがうかがえます。
ジヤトコ株式会社
ジヤトコ株式会社は、自動車用自動変速機の製造を手がける企業として、DX推進に向けて業務アプリ開発基盤をkintoneに一本化する決断をしました。
ローコード・ノーコードで直感的に扱えるkintoneを活用することで、現場の社員が主体となってアプリを開発・運用できる体制を整備。
専門的なコーディング知識がなくても対応可能となり、内製化への大きな一歩を踏み出しました。
さらに、運用ルールの明確化や、アプリ開発スキルの5段階評価制度、ITリテラシーを高める教育施策を導入したことで、社員の自発的な参画が促進されました。
これにより、現場から次々に新たな改善アイデアが生まれる強固な組織文化が形成され、IT内製化の好例として高く評価されています。
参考:事例から考える DX 内製化の課題と成功のポイントとは? 7 つの成功事例を一挙にご紹介!|
まとめ|IT業務の内製化をする企業メリット
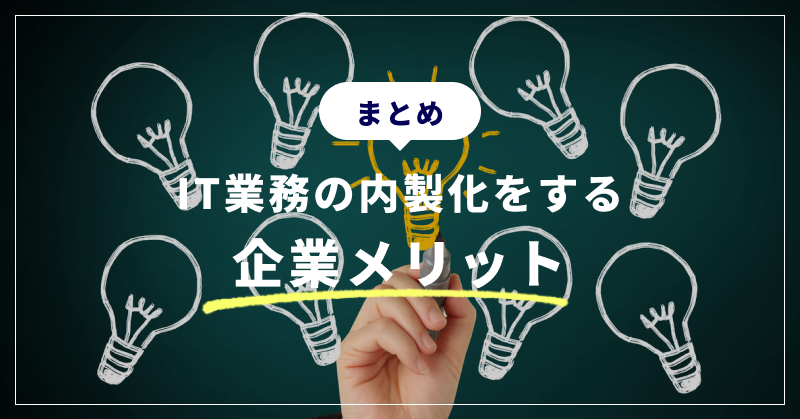
IT業務を内製化することで、外注コストを抑えつつ、社内にノウハウを蓄積できる体制が整います。
特に、外注先とのやりとりに時間がかかっていたり、対応の柔軟性に不満を感じている企業にとって、内製化は業務効率の改善につながるでしょう。
しかし、「何から始めればいいかわからない」「専任の人材がいない」といった不安があるのも自然なことです。
そんなときは、副業人材や業務委託などを活用し、まずは一部業務から小さく始めるのが現実的な第一歩と言えます。
私たち株式会社デイワンは、検討段階からハンズオンで支援し、方向性の整理から体制構築まで並走することが可能です。
リスクを最小限に抑え、内製化に踏み出すサポートをお約束します。
この記事を書いた人
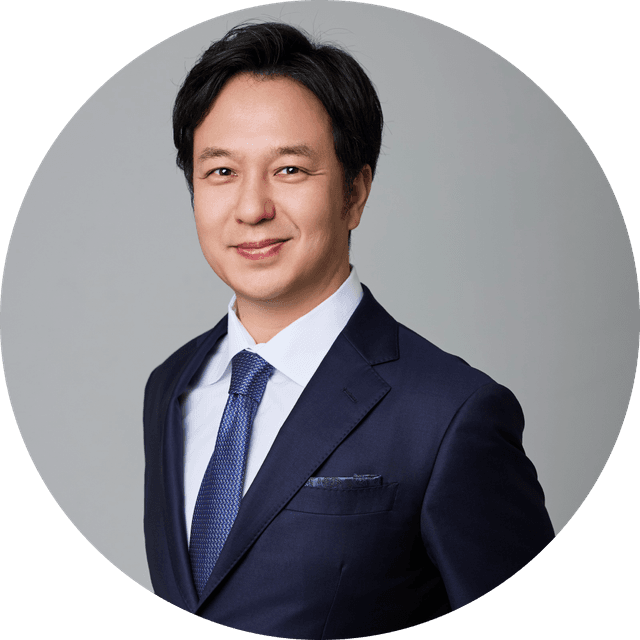
株式会社デイワン 代表取締役 月森 隼人
不動産コンサルタント、注文住宅やマンションなどの企画営業を経験し、大手広告代理店のデジタル部署にて、Web領域でのブランディングややディレクションなど上流から幅広く担当。


